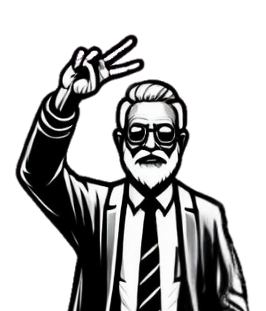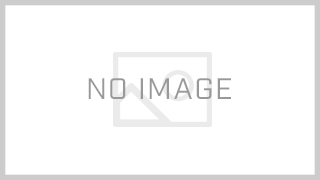🌿 ゆらぎながら育つ力
― 「整えすぎない」子育てと教育の話
ひじさん
どうも。ひじさんです。
かうへんがさん
どうも。かうへんがです。
よーへーさん
どうも。よーへーさんです。
かうへんがさん
最近、子どもを見ていると「落ち着きがない」「集中できない」って気になることが多いんです。
親御さんも「ちゃんとさせなきゃ」って焦ってしまう。
でも、完璧に整えようとするほど苦しくなる気がして…。
親御さんも「ちゃんとさせなきゃ」って焦ってしまう。
でも、完璧に整えようとするほど苦しくなる気がして…。
よーへーさん
うん、すごくわかります。
でも実は、“ちゃんとしすぎない”ほうが、子どもは伸びるんですよ。
自然の世界を見てください。木も川も、まっすぐピタッとは止まっていません。
風に揺れ、曲がりながら流れています。
それでも倒れないし、ちゃんと前に進んでいますよね。
でも実は、“ちゃんとしすぎない”ほうが、子どもは伸びるんですよ。
自然の世界を見てください。木も川も、まっすぐピタッとは止まっていません。
風に揺れ、曲がりながら流れています。
それでも倒れないし、ちゃんと前に進んでいますよね。
ひじさん
それはまさに“動的平衡(どうてきへいこう)”という状態です。
つまり「変わりながら安定する」こと。
生きているというのは、少し揺れて、また整う——その繰り返しなんです。
安定と変化の間にあるリズムこそ、生命の知なんですよ。
つまり「変わりながら安定する」こと。
生きているというのは、少し揺れて、また整う——その繰り返しなんです。
安定と変化の間にあるリズムこそ、生命の知なんですよ。
🧠 「ズレ」や「ゆらぎ」は、成長のサイン
かうへんがさん
なるほど…。でも“揺れる”とか“ズレる”って、なんだか落ち着かない感じもしますね。
それって、成長に必要なんですか?
それって、成長に必要なんですか?
ひじさん
はい。脳はいつも「こうなるはず」と予測しています。
でも現実は、その通りにならない。
この“ズレ”を修正しようと働くことで、脳は学んでいくんです。
でも現実は、その通りにならない。
この“ズレ”を修正しようと働くことで、脳は学んでいくんです。
よーへーさん
たとえば、階段が一段多いと思って足を上げたとき、「あれっ?」ってなりますよね。
その「思ったのと違う!」が、脳の学びのスイッチ。
だから、子どもの“間違い”や“失敗”は、成長のチャンスなんです。
その「思ったのと違う!」が、脳の学びのスイッチ。
だから、子どもの“間違い”や“失敗”は、成長のチャンスなんです。
かうへんがさん
そう聞くと、“失敗を減らすこと”より、“失敗を生かすこと”が大事って感じですね。
ひじさん
まさに。
完璧な状態は変化しない状態。
“ゆらぎ”があるからこそ、世界とやり取りして成長できる。
完璧な状態は変化しない状態。
“ゆらぎ”があるからこそ、世界とやり取りして成長できる。
🌾 「整えすぎない」って、どういうこと?
かうへんがさん
でも、親も先生も“整える”のが仕事だと思ってきました。
それを「整えすぎない」って、どういうことなんでしょう?
それを「整えすぎない」って、どういうことなんでしょう?
よーへーさん
整えること自体は悪くないんです。
ただ、“すぐ手を出してしまう”ことが問題。
子どもが転びそうになったら、まず手を出す前に「どうするかな?」と一瞬待ってみる。
その“考える余白”を残すことが、“整えすぎない関わり方”なんです。
ただ、“すぐ手を出してしまう”ことが問題。
子どもが転びそうになったら、まず手を出す前に「どうするかな?」と一瞬待ってみる。
その“考える余白”を残すことが、“整えすぎない関わり方”なんです。
ひじさん
自然の木も、人が添え木をしてまっすぐに育てると、
風がなくなった瞬間に折れてしまう。
でも、少し風に揺れながら自分でバランスを取った木は、根を深く張る。
教育も、育児も、それと同じです。
風がなくなった瞬間に折れてしまう。
でも、少し風に揺れながら自分でバランスを取った木は、根を深く張る。
教育も、育児も、それと同じです。
🌱 「不安定」は、悪いことじゃない
かうへんがさん
たしかに、子どもが揺れているときって、親のほうが不安になりますよね。
「大丈夫かな?」って。
「大丈夫かな?」って。
ひじさん
でもね、“不安定”は“壊れている”のではなく、“育っている途中”なんです。
安心して揺れられる環境があれば、自然と整っていきます。
安心して揺れられる環境があれば、自然と整っていきます。
よーへーさん
筋トレでも、まったくブレないフォームより、
少し揺れながらバランスを取るほうが、体幹が鍛えられるんですよ。
心も同じで、揺れながら自分の軸を作っていくんです。
少し揺れながらバランスを取るほうが、体幹が鍛えられるんですよ。
心も同じで、揺れながら自分の軸を作っていくんです。
かうへんがさん
じゃあ、親や先生ができるのは、
“揺れても大丈夫だよ”っていう雰囲気をつくることなんですね。
“揺れても大丈夫だよ”っていう雰囲気をつくることなんですね。
ひじさん
その通り。
子どもが揺れているとき、いっしょに揺れてあげること。
それが、いちばんの支援です。
子どもが揺れているとき、いっしょに揺れてあげること。
それが、いちばんの支援です。
まとめ
| 観点 | 言葉 |
|---|---|
| 子どもの成長 | まっすぐより、ゆらぎながら育つほうがしなやか。 |
| 親や先生の関わり | すぐ整えず、“待つ・見守る・揺れを許す”。 |
| 学びの本質 | 間違いは失敗ではなく、成長のきっかけ。 |
| 心の安定 | ゆらぎを受け入れると、自然に整っていく。 |
かうへんがさん
なんだかホッとしますね。
「ちゃんと育てよう」って肩に力が入ってたけど、
「揺れてても大丈夫」って思えるだけで、気持ちが軽くなります。
「ちゃんと育てよう」って肩に力が入ってたけど、
「揺れてても大丈夫」って思えるだけで、気持ちが軽くなります。
よーへーさん
そうそう。整いすぎた世界は息が詰まります。
風が吹くからこそ、木は強くなる。
子どもも同じです。
風が吹くからこそ、木は強くなる。
子どもも同じです。
ひじさん
そして大人も、です。
ゆらぎながら整う——それは子どもの成長だけでなく、
親や先生が生きていく上での“知恵”でもあります。
ゆらぎながら整う——それは子どもの成長だけでなく、
親や先生が生きていく上での“知恵”でもあります。
一言
完璧を目指すより、呼吸を合わせよう。
子どもといっしょに揺れながら、ゆっくり整っていけばいい。